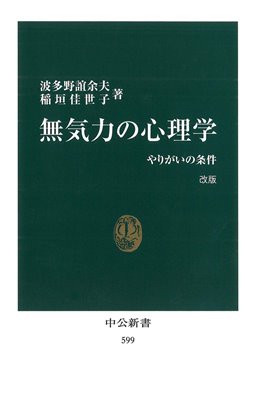ドラマ「刑事7人」
先日、ドラマ「刑事7人」を観た。内容は「8050」であった。高齢の父親は教授として現役で今も働き、妻は主婦という家族の中の、50歳になる一人息子が30年間引きこもるという設定で話が進んだ。この10年間は世間を騒がすなど奇異行動が絶えず、対して父親は謝罪し世間には公表することなく日を重ねていた。ある日、息子と母親が口論となり母は骨折をして横たわる生活を送っている。そのような矢先、父親の出張が決まり、不在中に息子が殺されたという事件である。
刑事の聞き込みが始まる。「息子が殺された、息子が殺したのではなくて?」と不審がる近所の主婦層が映し出された。場面が展開しながら<父親が犯人>・・・と疑いがわくが、最後に別人が浮上し犯人逮捕となる。
30年間の引きこもりの息子を思い、疲弊しているが両親は自分たち亡きあとのことを模索し悩み、世間に申し訳なく思い、自分たちの手で始末をするのがせめてもの救いと至ったのであろう。こうして夫婦の殺人計画かと思われたが違った。
この間、鑑識は決定打を見つけなければ・・・家庭に問題を抱え、引き際を考えている主任鑑識官は「父親ではない」ことを願いながら操作に協力し、焦りさえ見せるなど心の描写が際立った。
このドラマを観ながら複雑な思いがした。人はそれぞれの立ち位置から人を見るのだということを。
誰が悪いのでもない。取り巻く人々が気づいていながら手を指しのべることのない、社会で住む人々の意識を考えた・・・。
最近「ぼっち」という言葉に注目が集まっている。「社会と接点を持とうとしない人=危険」という偏見は絶対に避けなければならない。人は孤立せざる得ない状況になると、あえて他者を寄せ付けないようにしたり、これ以上傷つかないように自分を守ろうとしたりする傾向があります。好きで孤立する人はいなく、その人の生き辛さ、育ってきた環境、トラウマを理解しなければ孤独の理解には至らないのではないでしょうか。ひとり一人異なるつまずきをどう拾えるかが重要になります。孤独の感じ方はみなそれぞれ違います。生き辛さを抱えている人は「困った人」ではなく、「困っていると言えない人」なのです。
否定されることのない安心できる場所、自分はここにいてもいいと思える場所。社会との接点に悩む人たちに社会全体で向き合っていくことができるのを願うばかりです。